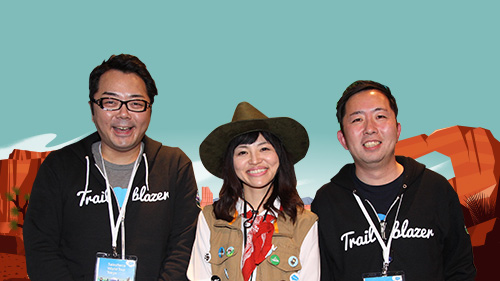Salesforceでは、企業のデジタルトランスフォーメーションを支え、革新に挑戦する人びとを「Trailblazer(トレイルブレイザー:先駆者)」と呼んでいます。「Trailblazer」の取り組みをご紹介している本連載(過去の連載記事はこちら「ユーザ企業編」、「開発者編」)。今回は、昨年開催された「Salesforce World Tour Tokyo 2016」のセッション「活用自慢チャンピオンが語る!Salesforce活用の秘訣」から、システム管理者の皆様の取り組みをご紹介したいと思います。
導入から定着化、そして更なる活用へ
株式会社サンゲツ マーケティング部マーケティング課 中野 慶介 氏
約1年半で約80%の営業業務を電子化、訪問件数重視からターゲットを絞り込んだ営業スタイルへ
株式会社サンゲツは愛知県名古屋市を本拠地とし、壁装材や床材、カーテン、インテリア商品などの企画開発・販売を行う企業。2014年に経営体制が変わったのを機に、営業本部が目指すべき姿を改めて明確化、これを実現するための基盤として2015年5月にSalesforceを導入しています。以前の営業現場は紙だらけで、訪問件数重視の営業スタイルでしたが、導入から約1年半が経過した現在では営業業務の約80%を電子化することに成功。営業活動のプロセスもダッシュボードで可視化され、ターゲット顧客を絞り込んだ効果的な営業活動が行われるようになっています。
しかしそこに至る道程は、決して平坦なものではありませんでした。実はサンゲツには、それまで約12年にわたって運用され続けてきたSFAツールが存在しており、「何故わざわざSalesforceを導入する必要があるのか?」という思いを、多くの社員が持っていたからだと言います。
導入後直面した3つの課題と、解決へのアプローチ
「導入後に大きく3つの課題に直面しました」と中野氏。それは「旧SFAツールへ戻せ!の乱」、「『いいね!』抵抗勢力との戦い」、そして中野氏が以前所属していた九州支社から強い抵抗を受けた「九州支社 大炎上&号泣事件」だと振り返ります。それではどのようにして、これらの課題を解決していったのでしょうか。
まず「旧SFAツールへ戻せ!の乱」に対しては、以前できたことをより効率的に行えるようにすることと、以前はできなかったことを「圧倒的なインパクト」でできるようにすることで対応しました。運用開始後2週間で200件以上出ていた改善要求の約8割を、運用開始後2ヶ月で解決。影響度の大きいものは個別システム開発も行い、運用開始後3か月で約9割の課題を解決したのです。旧SFAで12年かかっていたことを、Salesforceではわずか3ヶ月で成し遂げることができたと中野氏は語ります。
次に「『いいね!』抵抗勢力との戦い」では、「いいね!」を「確認しました」の意味で運用することを提案。メールのように一方通行ではなく、相手が確認したかどうかが双方向でわかるという、新たなメリットを訴求しました。このような発想の転換によって、「いいね!」も少しずつ受け入れられるようになってきたと言います。
最後の「九州支社 大炎上&号泣事件」では、全支社の利用度状況を比較し、営業生産性を可視化した上で、浸透の早かった東北支社の成功事例を共有。Salesforceの効果を納得してもらった上で、九州支社での現地フォローを行ったと説明します。「九州に出張した夜、諸先輩社員が続々と飲み会に合流し、『九州での借りは全国へ返せ!』という熱い激励をいただきました。その言葉に思わず私が号泣してしまったため、これを『大炎上&号泣事件』と名付けたのです。現在の九州支社は、全国8支社中、第2位の利用度になっています」。

Salesforceが最も可視化してくれるのは『人』
これらの課題解決と並行して、定着化へ向けた3つの取組みも進められていきました。
第1は基本業務マニュアルの作成。操作マニュアルだけではなく、画面キャプションをふんだんに盛り込んだ懇切丁寧な業務マニュアルを作成することで、浸透が急速に進んでいったと言います。
第2は柔軟なカスタマイズ対応。Salesforceから提供される年3回のバージョンアップに加え、独自の機能改善を月平均2.2回のペースで進めていきました。これによって、気がつけば「以前できなかったこと」よりも「Salesforceだからできること」の方が多いと、現場ユーザーに感じてもらえるようになってきたのです。
そして第3が組織横断型の「定着化プロジェクト」の発足です。全国から「マネージャー+直属部下のコンビ」でメンバーを選抜、テーマを絞り込んだ上で徹底的かつ確実に実行していきました。このようなメンバーの選び方をしたのは、上司と部下との間の温度差を生まないことが目的だと中野氏。またプロジェクトの会合はワークショップ形式を採用し、そこで作成されたダッシュボードを全国共通ダッシュボードにする、といった取り組みも行われています。
「結局のところ、Salesforceが最も可視化してくれるのは『人』だと思います。販売実績や活動実績、活動報告内容等でその部署や担当者の個性を可視化し、現状や傾向、異常値をいかに早く見つけ、必要な手を打っていくか。これを強力に支援してくれるのが、Salesforceだと信じています」。
営業個々の質を高めるためのSalesforce活用術

コネクシオ株式会社 法人ソリューション営業部 ソリューション推進一課 長尾 大輔 氏
すでに導入から9年、活用度は極めて高く売上増にも貢献
コネクシオ株式会社は、伊藤忠商事株式会社が1997年に業務受託会社として設立、その後数回のM&Aを経て成長を続けてきた、モバイル通信サービスの販売会社。国内3大キャリアの認定ショップ運営や大手カメラ・家電量販店の販売サポート等を行う「コンシューマ事業」と、法人相手に通信機器や関連サービス、モバイルソリューション等を提供する「法人事業」を展開しています。これらのうち法人事業の営業活動にSalesforceを活用しており、すでに導入から9年が経過。営業評価や業務に連動しているため、ログイン率99%等、極めて高い活用度になっています。
「携帯電話の法人営業では、お客様からの引き合いで商談が成立する『デイリー商談(受けの商談)』と、こちらから積極的な提案を行う『プロセス商談(攻めの商談)』がありますが、これらに合わせてレコードタイプを分けることで、商談の『質』を把握しています」と長尾氏。また商談フェーズの統一による見通し精度の向上や、失注案件の記録や分析によるリベンジ案件強化も行っていると説明します。「2013年の失注金額が10億円ありましたが、2015年のリベンジ商談でその17%をすくい上げることができました。これも含め売上高は2倍になっています」。
「なんちゃってマネージャー」によるミスリードが大きな問題に
このようにコネクシオでは、Salesforceが順調に定着し、その効果も上がっています。しかしツールが定着したことで、新たな問題も引き起こされたと長尾氏は指摘。それは「なんちゃってマネージャーの大量増殖」だと言います。
「なんちゃってマネージャーとは、営業会議で『予材が足りない』『訪問件数が少ない』『受注予定日が来たけど大丈夫?』といった、Salesforceのレポートを見ればわかることばかり発言する人のことを意味します。レポートが示す数字だけで判断すると、営業現場でのミスリードが生じます。例えば営業効率向上によって定例訪問回数を削減した営業担当社に対し、レポート上は訪問件数がダウンしているため、もっと訪問件数を増やせといった指示が出されてしまうのです。その結果、営業の質を高めるための情報集約・分析が、『数撃ちゃ当たる』スタイルへの逆行につながってしまいました」。
この問題を解決するため、コネクシオでは「成果の上がっている営業」と「なかなか成果の上がらない営業」の違いを、明確化するための調査に着手します。しかしSalesforceの指標だけでは判別は困難だと判断。そこで営業担当者との同行をひたすら実施、その結果「できる営業は『商談のコントロール』がすごい」ことを突き止めます。
「成功している営業担当者は、必ず状況の整理・確認から商談に入り、訪問毎にきちんとゴールを設定します。そして毎回相手の予算や承認ルートを確認し、商談を継続すべきか否かを判断していることがわかりました」。
営業の『行動』にフォーカスし、一人ひとりが自己成長できる仕組みを実現
この知見を元に、売れている営業担当者に共通する行動を、最小限の工数で正しくピックアップできる「活動オブジェクト」を作成。また「経緯」「目的」「ゴール」を、100文字以内で入力する項目も用意しました。これによって訪問内容を事前に把握できるようにし、商談の見込みも課題・予算・時期・決済等の観点から、正しく予測できるようにしたのです。現場リーダーは外出先からその中身を確認することで、活動のChatterフィードで訪問前にアドバイスを行えます。
それではこの「活動オブジェクト」の活用で、どのような変化が生まれたのでしょうか。「営業担当者に対しては、入力文字数を制限したことで要点を整理・把握する力がつく、目的を明確にすることで『とりあえず訪問』もなくなり、商談を確実に進める力がつく、という効果がもたらされました。また現場リーダーは、営業担当者の行動の見える化で的確なアドバイスが可能になり、見通し精度の向上にもつながっています」。
実際に営業経験が短い営業担当社を対象に1年間テストしたところ、対象者の売上額がこぞって上位にランクイン。的確な指示が行われたことで、訪問件数や商談作成数も自然と増加していったと言います。「営業の『行動』にフォーカスを当てることで、個々の営業にあったサポートを実施できるようになりました」と長尾氏。営業担当者と現場リーダーの双方において、一人ひとりが自己成長できる仕組みを実現しているのです。